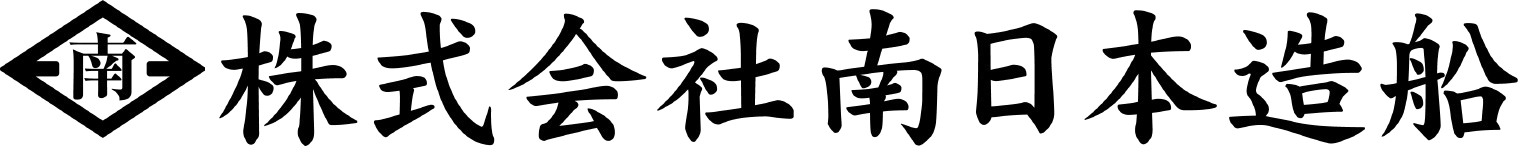PROFILE

S・M
設計グループ 艤装情報チーム
県内大学の機械電気工学科を卒業後、2021年に新卒入社。現在は設計グループ 艤装情報チームでエンジン場の配管設計を担当。入社4年目の設計者として日々スキルアップに励んでいる。
世界を巡る船には、大学の学びが詰まっている。
大学では機械電気工学科に所属し、材料力学、熱力学、電気回路など、幅広く工学を学んでいました。 正直、それぞれがバラバラに感じていた中で、ある日、研究室の先輩が南日本造船に入社したと聞きました。「大学の知識がすべて活かせる会社だよ」と教授に言われ、急に視界が開けたような感覚になったんです。
そして、実際に見た“船”。 巨大な鉄の塊が海に浮かぶ姿に、ただただ圧倒されました。他のものづくりでは、きっと味わえない“壮大さ”に衝撃を受けて、「自分も関わってみたい」と思ったのが、造船の世界への入り口でした。
9,000本の配管を、一本一本設計していく

自分の担当するエンジン場だけでも、なんと 約9,000本以上の配管が取り付けられており、すべてに図面が必要です。手作業ではなく、 パソコン上で3Dモデルで設計し、そこから図面を自動生成するスタイルが主流ですが、大切なのは、その図面が 現場で本当に扱いやすいかを考えること。
「この曲がり、現場で取り付けやすいかな?」
「工具を使うスペース、ちゃんと確保できてるかな?」
そういった“人の動き”を想像するのも、設計の仕事です。
困ったときはすぐに先輩に相談できる空気があって、チーム内で支え合いながら進められる、恵まれた環境にいると感じています。
ミスから学んだ仕事への向き合い方

しかもその日は、自分は休みを取っていて不在。 先輩が修正に入ってくれたおかげで、なんとか納期には間に合いましたが、多くの部署に迷惑をかけてしまいました。
でも、先輩は責めることなく、 「失敗そのものより、その後どう動くかが大切だよ」と伝えてくれました。 その言葉を、今でも自分の仕事のスタンスとして大切にしています。
“あの人の図面なら”と思ってもらえるように
設計には、 現場の視点が欠かせません。それが実感できたのは、入社して最初の1年間、実際に現場作業を経験したからです。
「この場所、狭くて身体が入りにくかったな」
「工具を当てる角度が取れなかったな」
現場でのあの実体験が、いま図面を引くときの“気づき”に繋がっています。
いつか、現場の人から 「あ、この図面、あなたが作ってくれたんだね。じゃあ安心だね」 そう言ってもらえるような設計者を目指して、日々の仕事に向き合っています。
“1年かけてつくる一隻”が、世界を巡る

一隻の船が完成するまでは、最低でも1年かかる。
だからこそ、完成後に行われる船主さんへの受渡式で、 全社員が集まり、船を見送るその瞬間には、言葉にできない達成感があります。
自分が関わった船が、世界を巡る旅へ出ていく。
その背中を見送るたびに、胸にじわっと熱いものがこみ上げてきます。
“今”の時代に合った船を、これからも。

安全性、環境への配慮、効率性── 設計者として求められる視点は、これからも広がっていくと思います。
でも、変わらないことがひとつあるとすれば、 ものづくりの面白さは、実際に関わった人にしか味わえないということ。
少しでも興味があるなら、ぜひ一度、現場を見に来てください。
高さ80mのゴライアスクレーンや、9,000本以上の配管が張り巡らされた船内を見れば、 きっと、数字では伝わらない“リアル”を感じられると思います