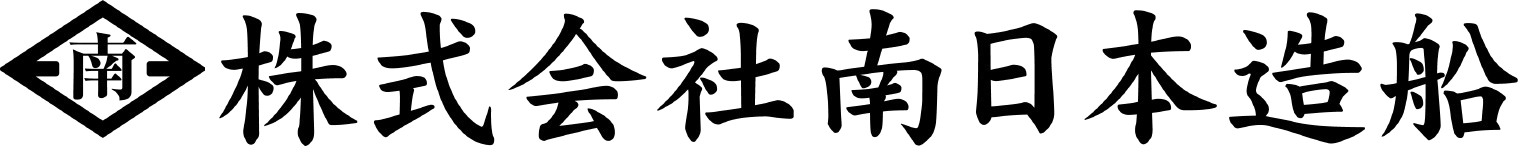PROFILE

U・D
機電装グループ 機装チーム
県内大学の機械電気工学科を卒業後、2024年に新卒入社。機電装グループ 機装チームに所属し、メインエンジンなど船の機関部分を担当。現場管理や工程管理、検査業務に従事している。
海の上の『街』という船のロマンに魅せられて。
大学では機械系の分野を学んでいて、正直、船に詳しいわけではありませんでした。「一度見学に行ってみたら?」と教授にすすめられて、なんとなく足を運んだのが、南日本造船との最初の出会いです。
当時の自分にとって船は、“大きな乗り物”という程度の認識でした。
でも、現地で聞いた「造船は街づくりに近い」という言葉が、ガツンと心に響いたんです。
実際に船内を見学してみると、エンジンルームや発電装置などの働く空間と、寝室・お風呂・トレーニングジムといった暮らす空間がひとつになっていて、
“職場と住まいが一体となった海上の街”という感覚でした。
しかもその街は、ただの比喩じゃないんです。
船の全長は200m~400mにもおよび、その中に“街の機能”が本当に構成されている。
電気、水道、空調といったインフラが整い、船員さんは数か月間、そこで生活する。
そのスケール感と機能美に、ロマンを感じて「こんな世界があったのか」と、一気に惹き込まれました。
“心臓部”を守る現場管理の仕事

現場での管理や工程調整、検査機関とのやり取りまで幅広く行っていて、とくに「メインエンジン」や「プロペラ」といった 船の心臓部に関わる作業は、0.1ミリのズレが大きなトラブルにつながることもあるため、緊張感は相当なものです。
でもそのぶん、 現場での自分の判断がそのまま“形”になっていく感覚は格別です。 「よし、これでいこう」と決断したことが、数ヶ月後に“船の動き”として現れる──責任の大きさとやりがいを、日々感じています。
"現場でしか覚えられないこと”の連続

造船は“経験工学”と呼ばれていて、マニュアルには書かれていないノウハウがとにかく多いんです。 たとえば図面上は問題なくても、「こっちの角度で締めたほうが楽だよ」とか、「このときは手順を逆にしたほうがうまくいく」など、現場の判断が品質を左右することもあります。
最初はわからないことだらけでしたが、素直に「教えてください」と言えば、職人さんたちは惜しみなくコツを伝授してくれるんです。
一人前になるには10年かかるとも言われていますが、それだけ“深い仕事”をしている実感があります。
若手の声に、耳を傾けてくれる会社
造船の現場って、「昔からこうしてきたから…」という空気が強いイメージがあるかもしれません。でも南日本造船では、若手の声もしっかり受け止めてもらえます。「このやり方の方が安全かもしれない」
「新しい技術を取り入れたら、もっと効率が上がるかも」
そんな意見もちゃんと聞いてもらえるんです。
もちろん、経験に裏打ちされた技術がベースにあるからこそ、 “若手の柔軟な発想”が価値になる環境なんだと思います。
「自分が成長していくのと一緒に、会社もどんどん良くなっていく」
そんな感覚があるのは、南日本造船の大きな魅力のひとつです。
これからの時代に応える、“船のかたち”をつくる。

「もっと安全に」「もっと環境にやさしく」「もっと効率よく」
──そんな声が日々、交わされています。
一隻の船をつくるには、さまざまな職人さんの力が必要です。
その人たちと毎日会話を重ね、ときにぶつかり、支え合いながら、“この船を、無事に、確かに完成させる”という共通のゴールを目指しています。
知らなかった世界に飛び込んで、失敗して、教えてもらって、また挑戦して。
少しずつ「現場で信頼される人」へと近づいていく過程に、今、やりがいを感じています。
だからもし、今のあなたが 「ものづくりって、ちょっと面白そうかも」とか「現場で働くって、なんかかっこいいかも」と思ってくれたなら──その“かも”は、きっといい入口になります。
まずは、見に来てみてください。
人と人が交わって、ひとつの巨大な船ができあがる現場。
その一端を、あなたにもぜひ体感してほしいです。
ちなみに──“就航前の船”を見られるフェスタ、あるんです

その年の内定者にはイベントに特別ご招待しています。
操舵室(ブリッジ)に入れることもあって、「宇宙戦艦ヤマトの操舵室みたい!」って声もあるくらい。運が良ければ、ビル2~3階分の高さがある巨大エンジンも見られるかもしれません。
たくさんの人の技術が集結して完成する、たった一隻の船。
ぜひ弊社にご応募いただき、その空気を、肌で感じに来てください。